
小丸川下流沿岸に発達する段丘群
第1章 各地域の地形・地質と風土
4.西都・児湯地域
宮崎平野の北半部から九州山地の一部にわたる地域で、西都市と高鍋・新富・川南・都農・木城の5町及び西米良村を含む、九州山地の山波が日向灘に向かって傾き下るところに宮崎平野が介在し、それを切る海岸線は直線状に南へ下る。九州山地の大部分は四万十累層群。その一角、西米良村・椎葉村と熊本県との境に市房山花崗岩体が標高1722m、祖母山・国見岳に次ぐ高山を聳立させている。また、木城・川南・都農の3町と東郷町にまたがる尾鈴山酸性岩体は、それまで漸次傾き下って来た山波のりズムを破って新たな傾動時塊を盛り上がらせ、東向の緩斜面には宮崎層群の基底礫岩が這い上がっている。

小丸川下流沿岸に発達する段丘群
宮崎平野の北部の特徴づけるものは段丘・扇状地群から成る台地で、これを開析する小丸川・一ツ瀬川などの沿岸には、比較的まとまった沖積低地が展開する。“原(はる)”と呼ばれているものは台地面を指し三ヶ月原・唐瀬原・国光原・茶臼原・新田原及び西都原などが平野の大半を占めて広がっている。台地を構成する地層は宮崎層群の砂岩・泥岩を更新世における氾濫原堆積物としての礫層が主であるが、更新世の海成砂泥層も挟まれている。
これらの台地は古代における生活の舞台で、多くの文化圏を形成していたらしく、西都原や新田原をはじめとして、多数の遺跡群が知られている。宮崎県には約3,000基の古墳があると言われ、そのうち約1,000基が西都・児湯地域に、更に約300基が西都原に集中している。西都原は標高20m前後と60m前後の段丘面に分けられるが、その境界付近に縄文前期の遺跡が、また20m前後の段丘面に弥生期の水稲耕作に関係した遺跡がそれぞれ発見されており、有名な古墳群はおもに60m面にある。今から、5,000〜6,000年前の縄文海進は恐らく一ツ瀬川沿いに遡上し、現在の妻あたりは深い入り江となっていたであろう。九州山地を背後地にひかえ、“都万湾”に突き出た平坦な岬。それが往時の西都原の姿であったろう。そこは自然の要害と広角の展望を備えた安住の地であり、また、狩猟・漁労にとっても絶好の食糧基地であったに違いない。その後の海退に伴い、“都万湾”は陸化して陸水に洗われ、そこに形成された沖積低地は水稲耕作地帯となるが、居住地は一ノ瀬川の氾濫を避けて20m段丘面に構えることとなった。そこ水田地帯を眼下に見下し、また60m段丘崖からの勇水が得られたであろう。また、背後に仰ぐ60m段丘面を聖域とし、ここに祖先の霊を祭ることとなった。60m段丘面を聖域化し、そにに鍬を入れることを畏れた背景には、地下水の水量水質保全と、段丘崖の侵食防止を兼ねた古代人の叡智がうかがわれるような気がする。
第2図 縄文中期における西都原付近の湾入状態推定図
(拡大図 80,204byte)
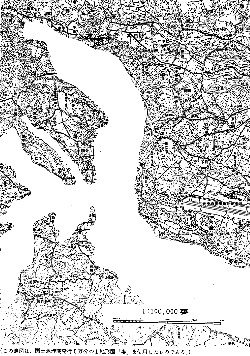
沖積低地の土地利用は、必然的に隣接する他の文化圏との交流を促し、新たなコミュニケーションと共同体の拡大によって、産業社会文明の新たな展開をもたらすこととなる。天孫降臨の物語には、山地から台地へ、台地から沖積低地へと、生活・生産の舞台の降下をたどった祖先の記憶と、高所を聖地視する深淵な思想が秘められているのかも知れない。古墳の構造は祖先のふるさとの景観を模式化したものとも読みとれる。縄文期以前の古代遺跡はほとんど台地か石灰岩洞窟である。本県には石灰岩も多いが、特に台地の発達が著しい。宮崎平野の段丘群、五ヶ瀬川沿いの阿蘇火砕流台地、そして西南部のシラス台地がそれである。古墳の方形は台地、円形は背後の山を象徴していると見ることはできないだろう。
なお、沖積層の基底深度は未だ分かっていないところが多いが、一ツ瀬川や小丸川沿岸では最大60m前後に達することが予想される。