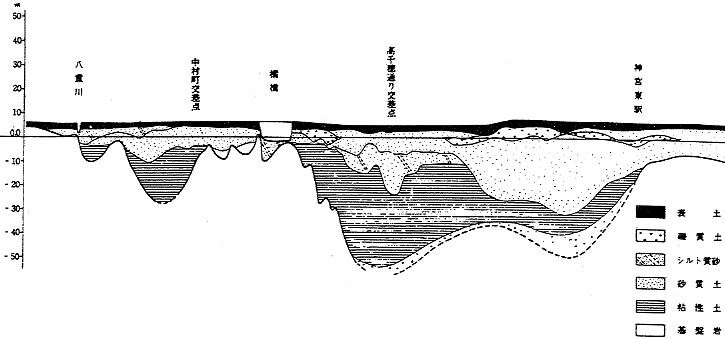
第2章 開発・保全と地質
3.都 市 基 盤
今日の都市は沖積平野に立地している場合が多い。沖積平野はデルタ地帯・氾濫原地帯・扇状地地帯などに区分されるが、防災上特に重視されるのはデルタ地帯である。そこは洪水・高潮・津波などによる被害を受けやすく、また軟弱な地盤が多い。都城市街地や小林市街地の大部分と、串間市福島の旧市街地、三田井・本庄などは旧扇状地や火砕流の作った台地上にあるが、宮崎市をはじめとして延岡・日向・日南などの諸都市は河口に近いデルタ地帯にある。
第5図 宮崎市における沖積地盤の推定断面の一例(宮崎市、1979による)
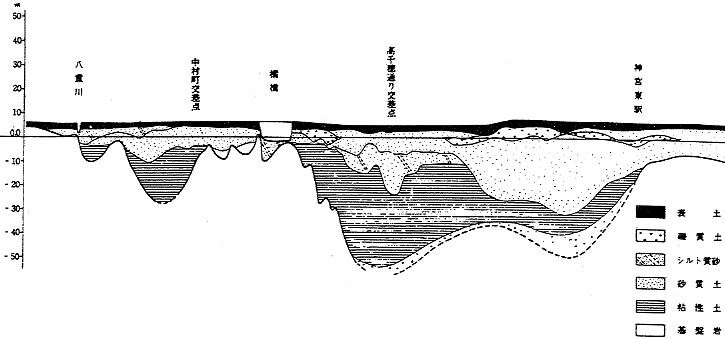
地盤沈下の規模や地震時の地盤の動きは、沖積層全体の厚さや軟弱層の存在とその厚さによって差が現れると考えられている。延岡や日向地区に深い埋没谷があることは既に触れた。宮崎市においては、最近多数の試錐資料に基づいて地盤図が作成され、沖積層の構造がかなり分かってきた。それによると、現在の大淀川が市街地の中心付近を横断するあたりは以外に沖積層が薄く、橘橋のたもとでは地表から数m程度で基盤の宮崎層群に達するところが見られる。これに大して大淀川の両側には埋没谷の形が認められ、その深さは左岸のもので60mに、右岸のもので30mに達している。これらの埋没谷は、一つは現在の大淀川に沿って上流に延びているが、他は宮崎層群丘陵地帯の樹枝状沖積谷に繁っている。これらの埋没谷には軟弱な粘土層が発達し、この意味でも防災上注意を要する。丘陵地帯の谷間は、むしろ災害緩衝地帯としての意味からも、また環境保全の立場からも、水辺緑地帯として維持されることが望ましい。