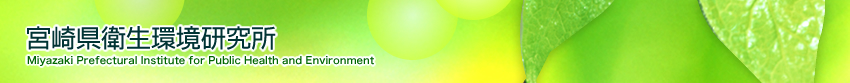|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 南嶋 洋一(委員長) | 古賀総合病院 臨床検査部長(宮崎大学名誉教授) |
| 山本 隆一 | 九州保健福祉大学 副学長 |
| 吉田 建世 | 宮崎県医師会 常任理事 |
| 後藤 義孝 | 宮崎大学農学部 獣医学科教授 |
| 杉尾 哲 | 九州河川研究所 代表 (宮崎大学名誉教授) |
別表2 調査研究課題に対する評価委員会の主な意見と所としての対応
食品と環境中からの病原ウイルスの検出方法の検討
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 食品と環境中からの病原ウイルスの検出方法の検討 研究期間 評価:5 |
意見1 | 本研究は、食品中や水環境からの病原ウイルスの検出限界を詳細に明らかにしようとするもので保健行政上重要な研究である。但し、現在の検出法では、充分な検出感度があるとはいえず、更に研究を発展させた新たな検出方法を開発し、今後は、より多くの食中毒関連ウイルスについて網羅的かつ迅速に検出できるシステムを構築していただきたい。 |
| 対応 | 検出感度の向上のために、Nested-リアルタイムPCR法による対応を検討している。主要な食中毒関連ウイルスの網羅的・短時間での検出については、マルチプレックス・リアルタイムPCR法等を検討していきたい。 | ||
| 意見2 | 今後、実際の事例の多くの材料で検出率を調べ、精度を上げて欲しい。 | ||
| 対応 | 保健所と連携して実際の事例で検討していきたい。また、国立研究機関と地方衛生研究所によるパンソルビントラップ法の共同研究で検査精度の比較と向上に取り組んでいく。 | ||
| 意見3 | パンソルビン・トラップ法で検出し得るノロウイルスの遺伝子型を明示して欲しい。 | ||
| 対応 | ヒト免疫グロブリン試薬のLot毎に、検出し得るノロウイルスの遺伝子型を検討し検査に用いる。 |
毒素原性大腸菌が複数検出された集団感染事例の検討
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 毒素原性大腸菌が複数検出された集団感染事例の検討 研究期間 評価:5 |
意見1 | 毒素原性大腸菌(ETEC)の病原遺伝子検出は意義のある手法であるが、細菌学的、感染症学的には菌の分離に基づく毒素や付着因子の証明も必要ではないだろうか。また、大腸菌集団中における毒素遺伝子陽性菌の比率も検討課題であろう。 迅速性という見地から、便中の病原遺伝子の直接検出ができないか検討して欲しい。 |
| 対応 | 遺伝子だけでなく病原因子の証明も重要と考えるので、引き続き菌の分離も実施していきたいと考える。今後、可能な限り釣菌し、比率を調べることで、釣菌数の指針となり得ないか検討していきたい。また、便からの直接検出も含めた、他の検出法も検討していきたい。 | ||
| 意見2 | ETECの胃酸耐性を標的にする視点は適切である。感染に個人差が見られる原因の解明の一つとして、今後つながっていくのではないかという期待もある。 | ||
| 対応 | ETECの耐酸性に関する統一された見解がないため、興味ある課題であり今後検討していきたい。 | ||
| 意見3 | 海外旅行者下痢症や食中毒の原因菌となるETECの研究は、海外旅行者が増加した今日の県民ニーズに対応している。また、感染の原因特定に関する食品の検討は県民の食についての安心・安全を確保する課題についての取り組みとして有益であると評価する。 | ||
| 対応 | 調査研究の結果が県民の生活の質の向上や本県の公衆衛生の発展に寄与できればと考えている。食品に関しては非加熱食品に着目し、現状の食品収去検査に付随し、野菜等を中心にした拡大調査を行う予定である。 | ||
| 意見4 | 今後起こりうる事例への注意喚起を目的に、ETECの多様性に伴った検査、行政、疫学面での対応を想定した研究で、海外旅行者が増加した今日の県民ニーズに対応している。研究成果が、いち早く県民にフィードバックできることを期待したい。 | ||
| 対応 | 今後、県民への情報提供のツールとして、HPや週報等を活用していきたいと考えている。積極的に情報を発信することで、検査、行政、疫学面等に貢献できればと考える。 |
微生物が関与する食品の臭気成分とその識別方法の検討
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 微生物が関与する食品の臭気成分とその識別方法の検討 研究期間 評価:5 |
意見1 | “官能検査”によっても、例えば緑膿菌など、いくつかの特徴的な菌は推定可能である。臭気成分による分離菌の機器的同定は十分期待し得る。それにはまず、特徴的な細菌を対象に、特定の食品成分と組み合わせたモデル実験が必要であろう。 |
| 対応 | 官能検査とGC/MS分析を並行して実施し、苦情の多い食品に増殖する微生物のモデル実験で確認したい。 | ||
| 意見2 | 食品の臭気成分を科学的に分析し、食品の微生物汚染の原因菌を特定しようとする本研究テーマは、非常にユニークで興味深いものである。食品の臭気をGC/MSで測定解析することで食品の微生物汚染の原因菌の種類、発育環境を識別することが可能となれば、迅速に食品の保存環境など対応策が検討されることになり、食品を扱う業界の利益は非常に大きいと推測される。3か年での研究成果を期待したい。 | ||
| 対応 | 食品の微生物汚染において、迅速な対応は健康被害の防止等、非常に大きな意味を持つので、成果をだせるよう計画的に研究を進めたい。 | ||
| 意見3 | 食品中の微生物は種類も多く、より多くのデータの集積が必要で、継続的な研究により、データベース化できれば、検査時間の大幅な短縮が可能であろう。 | ||
| 対応 | 苦情の多い食品から順に多くのデータを集積し、検査時間の短縮、製品管理などに役立つようデータベースの構築を図りたい。 |
宮崎県特産農産物中の残留農薬実態調査
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 宮崎県特産農産物中の残留農薬実態調査 研究期間 評価:4
|
意見1 | この研究による本県特産物の厳密な残留農薬の定量は、「食の安全」即ち安全な食を提供するという本県の責任・姿勢を内外に示すことにつながり、農産業支援の意味においても非常に重要な課題である。県産品の残留農薬を極力少なくするための行政からのモニタリングシステムの構築を期待したい。また、県内の「道の駅」では、様々な農産物が、生産者の氏名を明示して売られているので、この種の県産品も検査対象にし、検査結果の生産者へのフィードバックを行ってほしい。 |
| 対応 | 残留農薬が基準値以下であることだけでなく、可能な限り残留農薬を低減化してくことは、安全性確保の観点からも、農業支援の観点からも重要であると思われる。「道の駅」等で販売されている農産物についても検査を実施するとともに、本研究の利点である厳密な残留農薬の定量により得られた結果を生産者や行政関係機関へ情報提供することによりシステム構築の一助としたい。 | ||
| 意見2 | 国外から宮崎県に輸入された農産物についての残留農薬も気になる。県民が口にする食材の安全が常に守られているのかどうか非常に気がかりである。 | ||
| 対応 | 国外産の農産物については、輸入時に検疫所において残留農薬検査が実施されている。宮崎県においては、県が外部機関に委託することにより流通する輸入農産物についても検査を実施している。 また、輸入農産物については全国的に調査研究が多く実施されている現状があることから、本研究では調査の対象としていないが、これらの結果をふまえて今後については検討していきたい。 |
||
| 意見3 | 流通機構の発達により、県内産の農産物が広く県外に流通していることから、宮崎県産の農産物ブランドを守り、食の安全と安心に寄与するこうした調査研究は大切だと思う。ただ無数ともいえる農産物とそれらに使用される化学薬品の組み合わせに対し、一機関が対応できる能力は限られており、検査対象をどのように選抜するか、いつまで継続できるのかといった点で不安が残る。 | ||
| 対応 | 検査対象は生産量や市場におけるシェア等を考慮して選抜を行う予定である。調査研究期間は2か年を予定しているが、結果に応じて期間を延長することも検討したい。また、一機関として対応できる能力は限られているが、本研究の結果を公表することにより、他機関と情報を共有し、農薬適正利用のための研究の進展に繋げたい。 | ||
| 意見4 | 収去検査については、他県では生産・製造または販売される食品等に対して検査を行っている。県民の食品についての安心・安全を確保するには、販売食品についての検査も必要であることから、本調査研究の目的の位置づけを明確にすることが大切です。 | ||
| 対応 | 今回は、とくに県民の関心も高く、また今後の収去検査の品目の選定の参考とし、生産者の自主検査の推進にもつながるものとして、ターゲットをしぼり、まず「宮崎県特産物」中の残留農薬検査を行うこととした。今回の結果を得ることにより、収去検査において検査する農産物の幅を広げる等見直しに活用していきたい。 |
口蹄疫に係る埋却地の環境に関する調査研究
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 口蹄疫に係る埋却地の環境に関する調査研究 研究期間 評価: 4
|
意見1 | 口蹄疫の後始末として重要な調査である。生態系の底辺に位置する各種の分解菌に、大量に散布された消毒薬がどのように作用しているか知りたい。 |
| 対応 | 消毒薬が各種の分解菌にどのように作用しているかは推測の域をでない。しかし、埋却地の調査の結果、土中からメタンが発生したり、調査している湧水からTOC(全有機炭素)が高値を示していたこと等から、菌による有機物の分解が進んでいるのではないかと推察している。 | ||
| 意見2 | 臭気調査は、土質や降雨履歴などによって土壌内の通気性が大きく異なるので、結果に影響がでる。調査結果の解析として、土質や降雨履歴などの相違について吟味していただきたい。 | ||
| 対応 | 土質に関しては、家畜伝染病予防法第24条(発掘の禁止)の規定があり、埋却地は3年間は掘り起こしが禁止されており調査はできていない。しかし、埋却後3年経って、継続調査を実施する時、土質については調査方法を含め、関係機関と相談していきたい。また、降雨履歴については、地元気象台のデータを活用し比較検討したい。 | ||
| 意見3 | 大量の埋却物の地域環境に及ぼす影響を継続的に調査する事は本県の研究検査機関のみがなしうる事であり、得られたデータは非常に貴重なものになると思うので、今後も継続的に検査して欲しい。また、調査結果は速やかにフィードバックし、地域住民の健康・生活を守るという視点で調査研究を行っていただきたい。 | ||
| 対応 | 環境・衛生に対してどれ程の影響を及ぼしているのか究明するため、更にモニタリングを続けて情報を発信していきたい。 |
沖田川における河川環境調査−植物性プランクトンの分布と汚濁指標の関係−
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 沖田川における河川環境調査 評価:4
|
意見1 | 微生物の増殖はNaCl濃度に左右される。潮の干満の影響調査時にNaCl濃度を測定し、併せて、プランクトンの耐塩性や好塩性を調べてみてはいかがであろう。 |
| 対応 | 沖田川は感潮域であるため、干満の影響を把握するためにもNaイオンやClイオン、EC等を調査する予定にしている。赤潮原因プランクトンの詳細な解析から、NaCl依存性等の性質を調べ、沖田川赤潮の全体像を明らかにしていきたい。 | ||
| 意見2 | 赤潮の発生は、漁業関係者にとって重要事項であり、その発生状況やメカニズムが判明することは、漁業のみならず県民の生活を守ることに繋がり、成果を期待したい。 | ||
| 対応 | 期待に沿えるよう、水産試験場とも連携を図りながら調査研究を進めていきたい。 | ||
| 意見3 | 本調査では、笹目橋の総リンの値が他の観測点より高いことや、降水量との関係等にも着目する必要がある。また、河川環境調査においては、広範囲にわたる汚濁原因調査が必要であるので、河川流域の市町村と連携して取り組みを行っていただきたい。 | ||
| 対応 | 赤潮の発生には、窒素やリンといった栄養塩類の濃度や地形等多くの因子が関与することから、環境基準点の笹目橋だけでなく、周辺河川や海域を含めて調査を行う予定にしている。沖田川赤潮の発生は以前からみられており、沖田川水質は過去データの蓄積があるため、延岡市とも連携しながらその解析を行い、長期的な影響評価を目指していきたい。 |
県内河川の底生動物による水質特性についての研究
| 課 題 ◇ 研 究 期 間 ◇ 評 価 | 県内河川の底生動物による水質特性についての研究 研究期間 評価 :5
|
意見1 | 底生動物についての貴重な取組として有益であると非常に高く評価する。所のホームページには2011年五ヶ瀬川と祝子川の詳細結果が掲載されている。県が勧めている「五感を使った水辺環境調査」に平成23年度は延べ2,428人が参加し、この調査の指導者にとっては、研究所の結果は非常に参考になる。研究所のホームページの「水生生物を調べてみよう」にリンクを張るなどの工夫をし調査結果の活用を積極的に推進することを期待する。 |
| 対応 | 所のホームページには2011年五ヶ瀬川の詳細結果の掲載に続き、2012年には酒谷川と広渡川の底生動物の詳細結果を掲載予定である。今後も県内の主要河川の底生動物の詳細調査を予定している。調査結果についてはご指摘のように、所ホームページにリンクを張るなど活用ができるように、今後情報を発信していきたい。 |
宮崎県衛生環境研究所
〒889-2155 宮崎市学園木花台西2丁目3-2 / 電話.0985-58-1410 FAX.0985-58-0930