山 崩 れ
昭和47年7月豪雨時における真幸の災害は、直接的には土石流によってもたらされたものであるが、その土石流は後背谷頭部における崩壊を契機として発達したものである。そこは新第三紀安山岩類が熱水変質を受けて粘土化している部分に相当し、かつ地形的に水雨が集中しやすい場所であった。崩壊岩塊の背後には滑落崖が形成されており、岩塊が一体となってずり落ちた形跡が認められる。したがって、崩壊初期の状態から言えば地滑り性崩壊と言える。

南那珂山地に頻発する山腹崩壊
山崩れは梅雨前線や台風に伴う集中豪雨の度毎に九州山地や南那珂山地に頻発しているが、これが余り世間の注目を浴びないのは、本県山間部における居住地の立地条件に負うところが多い。それら居住地の大部分は山間凹地の中央部や中腹部平坦−緩斜面ないし段丘面で、しかも急斜面の直下を避けた場所に立地しており、山崩れや土石流の危険地帯は地元住民が祖先からの伝承によって最もよく知っていたことによると思われる。しかし、大正末期−昭和初期以降、自転車交通路の発達に伴って、渓流に接した沖積面上の集落や施設が増加し、昭和30年代以降、その傾向は一段と加速されている。また、社会構造の変革に伴って、危険地帯伝承の機会が減少する一方、機械力による急激な地形改変が進行しているので、山崩れや土石流による予想外の危険度は潜在的に増加していると考えられる。本県の山崩れに対する危険度判定材料は少なく、今後の課題として残されているが、地質的には泥質岩・凝灰質岩、及びそれらと岩砂・チャートなどが複雑に交互し、あるいは破砕された岩層地帯、それに過去の地滑り・崩壊二次堆積物の発達する地帯が注目されよう。また、表流及び地下水の集積といった水文条件も重要である。更に、類似の地形・地質条件のもとでは植生も重要な意味を持つ。経験的には50年以上の照葉樹林が密生している斜面における崩壊例は極めて稀である。
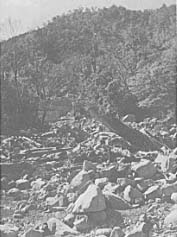
南那珂山地の谷間を埋める小規模な土石流跡