第3章 自然景観と地質
鵜戸山塊や鰐塚山周辺も、かつては極相に近い照葉樹林に覆われていた。昭和30年頃までの南那珂山地には猿の大群が我が物顔で跳梁する姿が見られた。今や当時の面影は、僅かに加江田渓谷や青井岳付近の一部に残されているに過ぎない。日豊本線青井岳トンネルから山之口側で見られる照葉樹林帯は、車窓景観として貴重な存在である。

鵜戸山塊の奥地に残る照葉樹林の極相
照葉樹林はシイ・カシ・タブ・クスなどによって代表される暖帯特有の樹林で、標高数100mまでの自然林を形成する。標高500mから、1,000m付近まで見られるモミ・ツガ・赤松林も本県の伝統的な自然林である。これらは霧島山・尾鈴山・大崩山及び祖母・傾の山々の針葉樹林帯を形成している。ブナ・ミズナラ林は東北地方の温帯樹林を代表するものであるが、本県でも標高1,100m以上の森林帯に生育し、祖母・傾連山をはじめとして、白岩山・国見岳・諸塚山など九州山地の奥地に見られる。
地質現象としての山地景観には二通りある。一つは雨風による侵食形であり、他は火山のように生成時の姿が残っているものである。侵食形はいわば岩と水の共同作製による彫刻であり、岩石の生い立ちのや堅さに応じて、いわゆる奇岩・奇石を生じ、あるいは瀑布を懸けるときにもてはやされる。これらが最も多いのは火成岩類である。大崩山から流下する鹿川と祝川は花崗岩特有の淵・瀞・滝・欧穴そして奇勝・奇岩としての節理に刻まれた岩肌を見せ、それぞれ鹿川渓谷・祝子川渓谷と呼ばれている。傾山に発源する日之影町も花崗岩の離れ島を通過するところに見立渓谷を作る。また、これらの河川が五ヶ瀬川に合流するためには環状岩脈の花崗斑岩の難所を通過せねばならず、そこに再び急流・急湍を作り、更には瀑布を懸けることとなる。尾鈴山塊も滝の名所である。矢研の滝をはじめ無数の瀑布群が山中深く連続し、行手を阻んでいる。
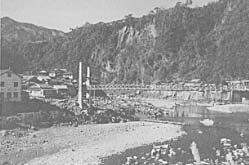
日之影に見られる阿蘇火砕流の段丘崖