2-2 四 万 十 帯
四万十帯は,宮崎県北部・中部で北東−南西トレンドを持ち,北西から南東に向かって白亜系諸塚層群,白亜系槙峰層群および古第三系北川層群,そして古第三系日向層群が配列する.諸塚層群の南東限は塚原衝上断層であり(村田,1998b),槙峰層群および北川層群の南東限は延岡衝上断層である(今井ほか,1979;坂井・勘米良,1981;村田,1996など).宮崎県南部では四万十帯は南北トレンドに近くなり,西から東に向かって,槙峰層群相当層の高隈山層(寺岡ほか,1981a),日向層群,日南層群が配列する.高隈山層と日向層群の境界は,延岡衝上断層である.このトレンドの変化は, 九州南部の北薩・人吉・野尻の各屈曲の影響であり(橋本,1962c;寺岡ほか,1981a;Murata,1987a,b),宮崎県の四万十帯は,熊本県人吉北東方の人吉屈曲と,宮崎市西方の野尻屈曲の影響を直接受けている.
第4図 九州四万十帯の地質概略図
拡大図(51kb)
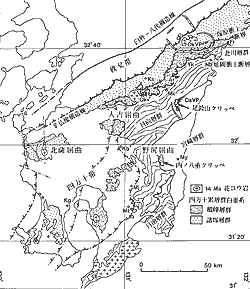
宮崎県20万分の1地質図および本書で用いる諸塚層群は,北限を仏像構造線,南限を塚原衝上断層(塚原断層)(今井ほか,1982;斉藤ほか,1996;村田,1998a,b)で挟まれた地帯に分布する砂岩優勢の白亜系を指す. これは,宮崎県北部の「椎葉村」図幅地域では佐伯亜層群(斉藤ほか,1996)に,「神門」および「諸塚山」図幅地域では,諸塚層群十根川層,椎葉層,日之影層(今井ほか,1979,1982)に相当する.また,諸塚層群は,五ヶ瀬川流域地域では坂井(1992a)の諸塚層群日之影層のうち北西側に分布するほぼ3分の2に相当し,「蒲江」図幅地域では,奥村ほか(1985)の諸塚層群椎葉層と八戸層,そして槙峰層の北西側のほぼ4分の3に,大分県「佐伯」図幅地域では,佐伯亜層群とこの付近の蒲江亜層群(寺岡ほか,1990)すべてがそれぞれ相当する.一方,ここで用いる槙峰層群は千枚岩優勢の白亜系を指し,「椎葉村」図幅地域では蒲江亜層群(斉藤ほか,1996)に,「神門」および「諸塚山」図幅地域では,諸塚層群長瀬層,槙峰層,八戸層(今井ほか,1979,1982)に相当する.また,槙峰層群は,五ヶ瀬川流域地域では坂井(1992a)の槙峰層群すべてと,諸塚層群日之影層のうち南東側のほぼ3分の1をあわせたものに,「蒲江」図幅地域では,奥村ほか(1985)の諸塚層群槙峰層の南東側のほぼ4分の1に相当する.特に,五ヶ瀬川流域地域と「蒲江」図幅地域などで,坂井(1992a),奥村ほか(1985)と地層区分が異なるのは,後述(4-2)のように,塚原衝上断層の位置に関する見解が異なることによる.
諸塚層群は砂岩優勢層で,主に砂岩からなる地層と,主に乱雑層(メランジュ相,混在相)および泥岩からなる地層が,北西傾斜の衝上断層で交互に繰り返している.槙峰層群は千枚岩優勢層で,砂岩,砂岩泥岩互層,玄武岩質火山岩類を伴う.北川層群は千枚岩および砂岩泥岩互層からなる地層で,槙峰層群とは古江衝上断層で接する(坂井・勘米良,1981;奥村ほか,1985).なお,槙峰層群および北川層群の砂岩,砂岩泥岩互層,玄武岩質火山岩類などの地層も,変成作用を受けている.
日向層群は,砂岩と乱雑層,泥岩の優勢な地層で,それらが低角な衝上断層で積み重なる(村田,1995).日南層群は主に乱雑層,砂岩,泥岩からなり,岩質的にも時代的にも日向層群と類似するが,日向層群より時代的に若い部分が含まれる(斉藤ほか,1996).なお,日向層群と日南層群の境界の断層がどこに位置するかについては,いくつかの考えが示されているが(坂井ほか,1987;木村ほか,1991;斉藤ほか,1994など),本地質図では,一致した見解とはなっていない.
宮崎県中部の都農町尾鈴山付近では,日向層群の上に,延岡衝上断層によるクリッペや,塚原衝上断層によるクリッペが存在する(村田,1991,1996)(第4図 51kb).また,宮崎市西方の日向層群の上には,延岡衝上断層による内ノ八重クリッペが存在し,その上には塚原衝上断層によるクリッペが存在する可能性がある(村田,1991,1998b)(第4図 51kb).