4−13 屈 曲 構 造
九州南部の北薩・人吉・野尻屈曲の中で(橋本,1962a,c;寺岡ほか,1981a;Murata, 1987a,b; 1987a;Kano et al., 1990;狩野ほか,1990),宮崎県内の地層が影響を受けているのは, 人吉屈曲の一部と,野尻屈曲である(第4図 52kb).これら以外にも,県北部での五ヶ瀬屈曲(寺岡ほか,1981a)や,県南部の三股付近の屈曲が存在する.三股付近のものは,本書では三股屈曲と呼ぶ(第25図).人吉屈曲は,すでに述べたように,宮崎県中部の西側の椎葉村,西米良村で,北東走向であった四万十帯の諸塚層群,槙峰層群,日向層群を,熊本県多良木町付近で南北走向に変化させるものである(寺岡ほか,1981a; Murata, 1987a)(第25図).屈曲した地層は,ほぼ南北走向,あるいは北北東走向で小林市北方まで達する.人吉屈曲は単一の屈曲ではなく,いくつかの屈曲の集合体である.この屈曲は,あらかじめ傾斜していた四万十帯の地層が,鉛直の軸を持った褶曲の影響を受けて回転させられたために,円錐状褶曲を作ることが明らかにされている(Murata, 1987a;狩野ほか,1990;Kano et al., 1990).
第25図 九州の四万十帯の屈曲の概略図
太線は,屈曲部での四万十帯の地層の一般走向を表す.地層は北西傾斜あるいは西傾斜のため,人吉・野尻・北薩・五ヶ瀬の各屈曲はアンチフォーム状,三股屈曲はシンフォーム状である.第4図や宮崎県地質図を参照.
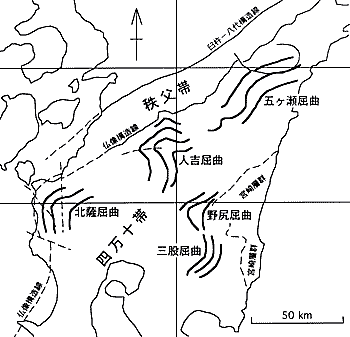
野尻屈曲(寺岡ほか,1981a)は,西都市,国富町,須木村で北東走向から東北東走向であった日向層群を,野尻町付近で,南北走向から北西走向に変化させるものである(第25図).屈曲した地層は,これらの走向で山之口町,三股町まで達する.屈曲部では,姶良火砕流堆積物(シラス)や段丘堆積物に覆われて日向層群の露出が限られているため,詳しいことは分かっていないが,釈迦ヶ岳から七熊山にかけて分布する厚い砂岩が,野尻町西方で佐土瀬から,高崎町高崎新田にかけての砂岩に連続するものと思われる.南北走向に近い高崎新田北方でも,ほぼ東西走向になっている部分があるので,野尻屈曲の内部には,より小規模な屈曲が伴われているものと予想される.すでに述べたように,釈迦ヶ岳から七熊山にかけての砂岩の南東限には,綾断層という北へ中角度で傾斜する断層が存在し,これを境として,北東走向の砂岩と,北北東走向の乱雑層が斜交して接している.この斜交性は,屈曲に伴って形成された可能性がある.
五ヶ瀬屈曲(金属鉱物探鉱促進事業団,1970;寺岡ほか,1981a;坂井,1992a)は,延岡市から日之影町にかけて,東北東走向であった四万十帯の諸塚層群,槙峰層群,日向層群を,五ヶ瀬川中流沿いの高千穂町三田井から延岡市川水流を結ぶ付近で,北東走向に変化させるものである(第25図).屈曲した地層は,この走向で北郷村,諸塚村付近へ達する.特に槙峰層群に屈曲の影響がよく表れているが,全体としてゆるやかな屈曲のため,そのヒンジを狭い範囲に特定することは難しい.なお,五ヶ瀬屈曲の南西部に当たる部分では,延岡衝上断層や,その上盤・下盤の地層に見られるように, 西郷村荒谷付近で北東走向から南北走向,南郷村神門北方では東北東走向,神門北西方からまた南北走向に近くなり,ゆるやかな屈曲がみられる.
三股屈曲は,野尻屈曲の南方の山之口町,高城町,高崎町付近で,南北走向から北西走向になった日向層群が,三股町付近で北東走向になるものである(第25図).人吉・野尻・五ヶ瀬の各屈曲が,凸部を西方または北西方に向ける屈曲であるのに対して,三股屈曲は,凹部を北西方に向ける逆方向のものである.
これらの屈曲は,四万十帯の最も若い地層である日向層群・日南層群の下部中新統が帯状配列した後,北薩屈曲地域の1400万年前の紫尾山花崗岩類,大崩山火山−深成複合岩体,尾鈴山火山−深成複合岩体,市房山花崗閃緑岩などが,貫入する前に基本的に形成されていたものと考えられる.その時期は,前期〜中期中新世(20〜15 Ma)であり,西南日本の時計廻り回転に伴って形成されたものと考えられている(Murata, 1987a,b;Kano et al., 1991).なお,杉山(1989)は,九州以外の他地域も含めて,これよりも若い時代の屈曲が存在することを明らかにしている.