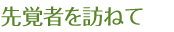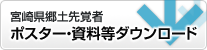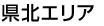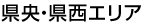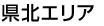

牧水公園内にある記念文学館は牧水生誕120年に合わせて新築されました。
かつて牧水が眺めていた坪谷の自然豊かな風景の中で、近代文学の世界をゆったりと楽しめる施設です。

1845(弘化2)年、祖父健海によって建築され、1階部分は当時病院として使われていました。 築160年以上が経過する生家は当時の面影をそのままに1966(昭和41)年、宮崎県の史跡として指定され、一般に公開されています。

牧水公園展望台からは牧水が愛したふるさとの景色を一望でき、ゆっくりと散策を楽しめます。公園のいたるところに牧水の歌碑があり、坪谷の自然を満喫しながら歌碑めぐりをしてみるのもおススメです。

勇吉が第1回懸賞飛行大会や初めての郷土訪問飛行を共にした「富士号」のプロペラをはじめ、日本人初となった1等飛行士操縦士の免状、遭難時に焼け残った遺品などを見る事ができます。

太平洋に輝く太陽と、勇吉が果たすことのできなかった太平洋横断無着陸飛行の姿を彫刻したレリーフがはめ込まれています。

勇吉の生家のあった延岡市南町(旧・NTT延岡支店敷地内)の一角にある生誕の地碑。現在は延岡市妙田緑地公園の後藤勇吉像の隣に移設されています。

銅像の傍らには勇吉が亡くなった際に詠んだ野口雨情の弔詩も建立されています。また、同じ型の銅像が勇吉が初めて初飛行に成功した門川町尾末の門川海浜公園にも建立されています。

1935(昭和10)年春、全国3番目の牧水歌碑として建立されました。毎年春分の日に歌碑まつりが開かれています。

牧水の母校 宮崎県立延岡高等学校(旧 宮崎県立延岡中学校)内の歌碑は、1957(昭和32)年 牧水の30年忌に建立されました。

生家裏山にある巨石には牧水が「文学か故郷か」で思い悩んだ時の心境を詠んだ歌が刻まれています。

牧水歌碑の中でも最新のこの歌碑は2010(平成22)年2月、牧水没後80周年・喜志子没後40周年を記念して建てられました。

高千穂峡にある牧水歌碑。東京から陸路中国地方を回って帰郷した際に詠まれたもので処女歌集「海の声」に掲載されています。
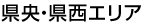

安井息軒旧宅の向かい側。入るとすぐ安井息軒展示室があり、多くの史料とともにその生涯と業績を知ることができます。

国の指定文化財。1994(平成6)年に元の茅葺き屋根に戻すなど史実に沿って整備・復元され、宮崎市清武町中野地区に保存されています。

高鍋信用金庫清武支店の南側に、息軒の妻・佐代にちなんで名付けられた「佐代橋」があります。佐代が生まれ育った実家(清武郷今泉村岡)がこのあたりにあったとされています。

高鍋町中央公園内の石井十次像。児童救済に生涯を捧げた十次の思いがしのばれます。

1873(明治6)年1月15日、宮崎県(第一次)設置とともに宮崎郡上別府村(現・宮崎市橘通東2丁目)に、県庁舎が置かれました。

「宮崎県の父」川越進の胸像は、宮崎県庁本館と議会棟の間に設置されています。

東諸県郡穆佐(むかさ)村白土坂(しらすざか)にあったと言われる生家の近くにあり、国指定史跡・穆佐城跡の西側に位置する曲輪(くるわ)を利用して作られています。

高木家の墓地は、宮崎市高岡町穆佐小山田地区にある、共同墓地の一角にあります。墓石側面には、兼寛が海軍軍医として東京に移り住んだということが書かれています。

穆佐から西へ約5Km、宮崎市高岡町内山の高岡城(別名・天ケ城)址に建つ、天守風建築の資料館です。

木城町にある石井記念友愛社内。「石井十次の会」事務所となるこの建物は、岡山から移築したもので“方舟館”とよばれています。

1979(昭和54)年、石井記念友愛社の敷地内に建てられました。十次の日記をはじめ関係資料約2000点を収蔵。奥の壁に作られた芹沢銈介作のステンドグラスには、キリスト教を厚く信仰した十次が描かれています。

高鍋町馬場原に今も残されている石井十次生誕の家。現在居住されており、外観のみ見学できます。

茶畑が広がる茶臼原の一角に、孤児たちの墓に囲まれて石井十次の墓があります。近くに、十次の胸像と茶臼原憲法の石碑も建てられています。

県総合文化公園内には小村寿太郎、川越進、石井十次、若山牧水、高木兼寛、安井息軒の銅像が設置されています。

文化の杜 敷地内の資料館と図書館に隣接しています。1994年(平成6)年2月、えびの市によって建立されました。


日南市出身の先覚者 小村寿太郎の没後80年の記念として平成5年に開設され、令和4年3月にリニューアルしました。日本外交の礎を築いた明治の外交官、小村寿太郎の生涯や偉業がミニシアターで紹介されています。

本町通り(国道222号)から飫肥城への案内板を入ってすぐ。小村寿太郎の生家があった場所で、生家は大手門から東に続く武家屋敷通りに移築されています。

飫肥藩主伊東家の墓所がある五百撰(いおし)神社西側の墓地の一角にあります。小村寿太郎は神奈川県葉山で永眠。東京の青山霊園にも墓所があります。

元々は現在「小村寿太郎侯誕生之地」碑がある場所に建っていましたが、明治時代後期に振徳堂裏手に移築され、1921(大正10)年に武家屋敷通りの現在地に再び移築されました。

県立日南高校の西側にある桜の名所。グラウンドなどが整備され、公園の奥まったところに小村寿太郎の銅像があります。

1831(天保2)年に飫肥藩13代藩主・伊東祐相が、元々あった学問所を大きく増改築し、中国の孟子の教えから校名を「振徳堂」と名付けました。

振徳堂西側にある銅像。隣には寿太郎を導いた小倉処平の碑もあります。

飫肥城大手門は1978(昭和53)年に復元されたもので、城内の石垣など当時をほうふつとされる雰囲気が漂います。城内には松尾の丸、歴史資料館、本丸跡などがあります。

1977(昭和52)年国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された飫肥城下の町並み。武家屋敷の門構え、生け垣、用水路などが地域の人々の協力で大切に保存されています。

終戦後初めて(1947(昭和22)年9月))建立された歌碑です。1907(明治40)年夏、青島、鵜戸、油津、都井と牧水が南九州を訪れた時の事を詠んだものです。
 ホーム
ホーム