


 |
 |
 |
|
銀鏡神楽のびやかな田園地帯が広がる西都市から一ツ瀬川に沿って遡(さかのぼ)っていくと、あたりは緑深い山々が連なる景色へと一変する。かつて東米良(めら)と呼ばれた銀鏡(しろみ)周辺は、険しい土地ながら縄文時代から人が住み、さほど遠くない時代まで焼畑や狩猟を中心とした山の暮らしが営まれてきた。 稲作に頼らない山の暮らしは、食料や富の貯蔵が困難であるため、人は自然の恵みにより深く感謝し、自然の脅威をおそれながら、山に寄り添うように生きてきたのだろう。神楽がその土地の暮らしや歴史を映す鏡であることを、銀鏡神楽は教えてくれる。 次々に降臨する神々12月14日から15日にかけて、銀鏡神社の大祭に奉納される銀鏡神楽は、周辺に点在する宿(しゅく)神社、六社(ろくしゃ)稲荷社、手力男(たぢからお)社、若男(わかおう)社、七社(ななしゃ)稲荷社から神々を迎える「神迎え」の儀式で始まる。「神迎え」は「面さま迎え」とも呼ばれ、銀鏡では神楽面そのものが神様として考えられている。これらの神々が次々に舞い降りる神楽の前半は、神主や宮司によって舞われる厳粛なものだ。 各地から集まってきた神々が銀鏡神社に向かう行列を、人々は手を合わせて迎え、神楽の夜は静かに始まる。もっとも重要な番付とされる西之宮大明神(懐良親王(かねよししんのう)。銀鏡神社の主神のひとつ)の舞いは、代々銀鏡神社の神主によって舞い継がれてきた。神楽の夜の舞手は、人を越えた存在として扱われ、当日、神主が口にするものは、座付(ざつけ)と呼ばれる取り仕切り役が毒見をしてから供するのがしきたりだ。また、一切のまかないものは、近年まで男だけで作り、台所の長として目代(もくだい)という役が脇差しをつけて目を光らせていた。 番付の前半では、このように神々が次々に降臨するのだが、その中に鵜戸(うど)神楽、鵜戸鬼神と鵜戸神宮に関するものが二番あることが目を引く。記録によると元和元年(1615)、鵜戸神宮(当時は鵜戸山道場)の別当を務めた浜砂淡路守が銀鏡に帰郷して伝えたとされる。もともと東米良周辺は竜房山(りゅうぶさやま)を仰ぐ山岳信仰の地であり、当時修験道の一大聖地として知られていた鵜戸山の神を招くことは自然なことだったのかもしれない。 山への祈り、シシトギリ銀鏡神楽の特徴のひとつとしてシシトギリ(狩法神事)がある。山の神である大山祇神とその娘・石長姫をまつる銀鏡神社の大祭だけに、山への感謝と祈りが祭りの基調となっているのだが、シシトギリは神楽の最終盤、すっかり夜が明けた後に、神事として行われる狂言劇だ。
これは猪狩りの様子を模したもので、本殿ではなく外神屋で行われる。厳粛な雰囲気で舞われるそれまでの神楽と違い、ユーモラスな問答と所作に人々の歓声が沸き、神楽の最後に村人の心をひとつにする。続いて神送りが終わると、神前に奉納されていた猪の肉で作った雑炊が参拝者にふるまわれ、ここで神楽は終了するのだが、祭りはまだ続き、翌朝、銀鏡川の川原で、「ししば祭」が行われる。これは山の恵みに感謝し、猪の霊を慰めるための祭りで、祈りを捧げた後に猪の頭を焼き、串に刺して食べる神事。派手な祭りではないが、狩猟文化の歴史と重みを感じさせてくれる。
法者に聞くお二人にとって銀鏡神楽とは? 武俊さん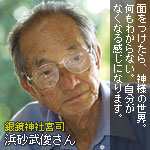 私は宮司で舞手ですから、とにかく一所懸命にやるだけなのですが、神前奉納ですから厳しさがありますね。真剣に舞うこと。人に見せるものではない。そういう風に昔から教えられてきました。 私は宮司で舞手ですから、とにかく一所懸命にやるだけなのですが、神前奉納ですから厳しさがありますね。真剣に舞うこと。人に見せるものではない。そういう風に昔から教えられてきました。武畩さん 銀鏡神社の神様は、とても力がある、怖い神様なんです。子供の頃から、そう叩き込まれました。これは銀鏡の人は皆そうでしょう。ありがたい神様なのですが、親しみがわくというものではなくて、おそれの方が強いですね。「奉仕を始めたら、終生奉仕しろ。そうでないと運が良くないぞ」と。ですから神楽に関わる者は、とにかく懸命に奉仕するだけで、人がどう見るかとか、観光がどうとかは考えられません。 武俊さん 私の記憶する中だけですが、昔そのままですね。何も変わっていませんし、変えてはいけないものでしょう。装束も、舞いも、人の心も、昔のままです。 舞っている最中は、どんな感じなのでしょうか。 武俊さん
|