ここで、建物に使う木材(梁・桁・柱など)の曲げ性能を対称に、「強い」、「弱い」について考えてみましょう。表1の曲げヤング係数(平均)、曲げ強さ(平均)、基準強度をご覧下さい。
|
| 表1 建築に使う木材(梁、桁、柱など)の曲げ性能 |
| 樹種 |
個数 |
曲げヤング係数 |
曲げ強さ |
平均
(kN/mm2) |
変動係数
(%) |
平均
(kN/mm2) |
変動係数
(%) |
基準強度 |
| ベイマツ |
1,000 |
11.6 |
20 |
45.3 |
35.4 |
22.8 |
| ソ連カラマツ |
270 |
12.6 |
19.1 |
51 |
28.8 |
26.7 |
| ヒノキ |
819 |
10.5 |
13.3 |
53.2 |
20.4 |
35.5 |
| カラマツ |
1,215 |
8.9 |
20.7 |
42.1 |
24.7 |
26.5 |
| アカマツ |
769 |
10.2 |
22.3 |
43.7 |
33.5 |
27.3 |
| ベイツガ |
466 |
10.3 |
21.9 |
43.3 |
36.1 |
17.3 |
| エゾマツ |
1,000 |
10.1 |
17.7 |
41 |
24.4 |
24.8 |
| トドマツ |
605 |
9.3 |
15.4 |
39.5 |
21.1 |
24.8 |
| スギ |
12,213 |
7.4 |
23.6 |
39.8 |
21.5 |
26.4 |
| ヒバ |
315 |
9.8 |
14.7 |
45.2 |
21.9 |
29.7 |
|
| |
| これらのうち建築に使う木材の「強い」、「弱い」はどの値の大きさを言うのでしょうか?勿論ヤング係数ではありません。では、曲げ強さ(平均)でしょうか?これも違います。正解は基準強度です。詳細な説明は割愛しますが、木材の強さは同じ樹種でも1本1本で異なり、ばらつきがあります。そのため、安全性を考慮して、実大材の弱い方から5%目の強さを基準強度として(図3参照)、建物の設計に用います(JAS材の場合、建設省告示1452号)。 |
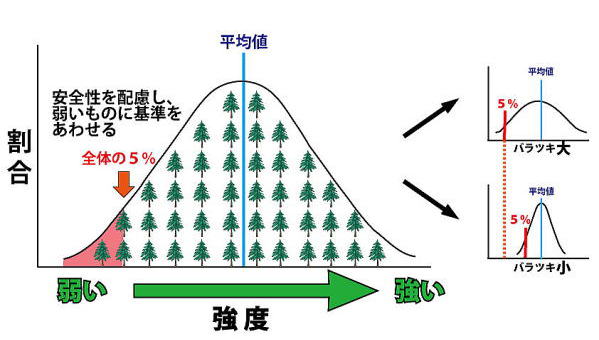 |
図3 木材の強さの分布
|
実は、この基準強度と曲げ強さ(平均)は、表1に示すように必ずしも対応していません。例えば、同表におけるスギの曲げ強さ(平均)は弱い方から2番目の値ですが、基準強度では真ん中くらいの値になります。これは、主としてバラツキ(変動係数)の差異に基づくもので、たとえ平均値が小さくても、バラツキが小さければ設計用の基準値(基準強度)は高くなる、ということを意味しています。このように、建物につかう木材の強さは安全を考慮した値であり、実用上平均値を用いることはありません。
補足ですが、構造材の性能を「強い」、「弱い」だけで判断し、材料選択を行うことは必ずしも適切とは言えません。設計用の基準値(基準強度)は、あくまで構造設計のベースとなる値であり部材の断面寸法を決定するための値なので、「強い」、「弱い」ではなく「数値が明らかにされていること」が重要なのです。 |
| (木材加工部長 農学博士 荒武志朗) |