| 宮崎周辺地区 |
宮崎市周辺の加江田・曽山寺・内海などでは天然ガスが地表に湧出している所が知られている。これらの徴候地では古くからガスを自家用燃料として使用したり、付随水を浴用に利用するなど、小規模な利用が行われていた。昭和30年代前半には本地域は特に重視され、地質・地化学等各種調査とともに多くの試掘も行われたが、経済的事情等により企業化には至らなかった。
本地域のガス層である宮崎層群は全体としては東に向かって緩く傾く単斜構造をしているが、高岡町柞ノ木橋や宮崎市鏡洲には四万十累層群からなる基盤の高まりがあり、宮崎周辺はこの基盤の突出部の間の湾入部に当たる。本地域での宮崎層群は基底より田野・綾・高岡・倉岡・大淀の各部層に区分されている。各々の岩相をみると、田野部層は細−中礫岩および中−細粒砂岩を主とし、浮遊性有孔虫化石により約580万年前に堆積を開始したと推定されている。層厚は50〜200mである。綾部層は暗灰色泥岩を主とし泥勝ち互層をまじえる。層厚は綾町付近では数100mに達するが、南北へ厚さを減ずる。高岡部層は泥勝ち互層を主とし、厚さ10m前後の砂岩層を伴うことがある。南部では一部に中礫を伴うこともある。層厚は300〜500mである。倉岡部層は砂勝ち互層を主とし、全体的にリズミカルな互層である。層厚は数100〜1,000mを有する。大淀部層は泥勝ち互層を主とするが、下−中部には砂勝ち互層や砂岩も挟在する。これらの地層は佐土原地区に比べると固結の程度はやや進んでいるものの、部分的には固結していない粗粒堆積物も多い、ガス層としては有望である。特に本地域ではガスだけではなく、付随水中のヨウ素も期待される。
次に本庄川流域の泥岩試料による有機物量の分析結果を第6表に示す。この結果抽出有機物量(ソックスレー抽出量)についてみると、以下のように3群に分けられる。
| 四万十累層群 | 0.0073% |
| 田野部層〜綾部層下・中部 | 0.0143% |
| 綾部層上部〜都於郡部層下部 | 0.0303% |
ここで注目されるのは、見掛け上よい母層とされていた綾部層下・中部の抽出有機物量が意外に少なく、綾部層〜都於郡部層上部のものの平均値の半分以下であるということである。また本地域の宮崎層群の石油化度は平均0.0088である。これら有機物量から宮崎層群の泥質岩のガス母層としての性質は新潟油田上部新生界のものより劣るが、南関東ガス田のものより優れ、沖縄南部ガス田のものに匹敵すると考えられている。
本地域でのガス・付随水の分析値は第7表に示すとおりである(第17図)。ガス質・水質をみるとこれもいくつかのタイプに分けられる。その関係は以下のようになる。
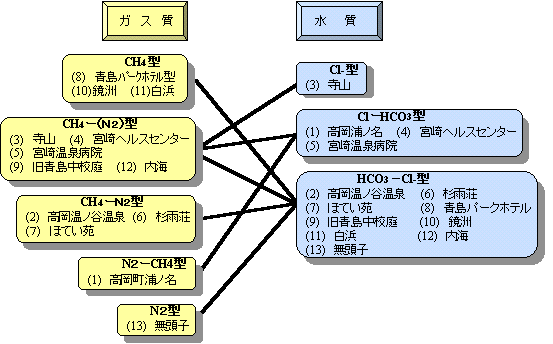
このことから、本地域のガスのうち、純粋に宮崎層群起源のガスはCH4を95vol%以上含み、N2は基盤の四万十累層群(日南層群を含む)よりの供給と考えられる。なお本地域の地下の温度分布については、T(゜C)=16.8+0.0266D (Dは深度;m)と推定される。
日南海岸北端の青島付近では、曽山寺−加江田の線をもって、これより南部の宮崎層群の砂岩はガス貯留層としては膠結度が高すぎるので、主に断層破砕帯等にガスを求めるべきであろう。
先にも述べたように、本地域では現在も一部でガスの都市ガス利用・付随水の温泉利用がみられるものの、本格的な開発は行われていない。しかしながら宮崎市という消費地を包含する点では本地域は最も有利であり、近い将来都市ガス原料としてのガス採取・付随水からのヨウ素採取等開発が本格的に行われるものと期待される。
また宮崎平野の全面に広がる日向灘一帯も天然ガス田として注目に値する。