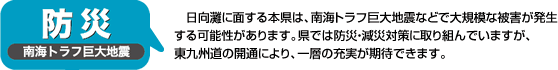
|
| |

|
|
●新・宮崎県地震減災計画の策定
南海トラフ巨大地震に対する防災力の強化や減災対策として、今後取り組むべき総合的な対策を取りまとめた「新・宮崎県地震減災計画」を策定しました。今後想定される被害を限りなく減らすための取り組みを進めていきます。
●地域防災力の強化
大規模災害時などの初動の要となる自助・共助を推進するとともに、地域での防災力の核となる防災士を養成しています。県民の防災意識の啓発をより一層進めるため、今年度も県内各地で様々な取り組みを進めます。 |
 |
 (1)命の道としての高速道路 (1)命の道としての高速道路
南海トラフ巨大地震では、強い揺れや津波被害により主要交通基盤である国道10号、国道220号、日豊本線、宮崎空港、各港湾の甚大な被害が想定されます。
このような中、東九州道は、被災者の救援・救助、人的・物的輸送などを行うための「命の道」として重要な役割を果たすものと期待されます。
|
| |
 (2)実践的な総合防災訓練の実施 (2)実践的な総合防災訓練の実施
平成25年度は、南海トラフ巨大地震を想定した、本県初の実践的な防災訓練を実施しました。今年度は、県北地域を被災地として、高速道路を活用した救援・救助、物資搬送等の訓練などを行い、東九州道が「命の道」としての役割を十分果たせるよう、平常時から備えていきます。
|
| |
 (3)避難所としての高速道路 (3)避難所としての高速道路
沿岸部の市町においては、津波からの一時的な避難場所の確保として、民間ビルなどを活用した避難ビルの指定が大きく進められたほか、高台や高速道路の法面を活用した避難場所の整備などを行っています。
現在、高速道路を活用した避難場所は、3市町・4か所で整備されています。
|
| |
(4)後方支援拠点の機能強化
大規模災害時に救援・救助・消火・医療救護活動やその後の復旧活動などを行うために、自衛隊、警察、消防、DMAT(災害派遣医療チーム)などの広域支援部隊が迅速に集結し、活動の拠点とする「後方支援拠点」を平成24年度に9か所、平成25年度に3か所指定しました。
東九州道の開通により、関係機関の活動の迅速化が大きく期待されます。 |
| |
 (5)広域連携体制の強化 (5)広域連携体制の強化
九州8県と国の出先機関などでつくる「南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会」や、知事と沿岸部の10市町長でつくる「宮崎県津波対策推進協議会」を通じて、関係機関との情報交換や連携強化を図りました。
東九州道の開通により、今後の九州内の関係機関による広域的支援が円滑に行えるほか、沿岸部の関係市町において、救援物資の受け入れ場所の確保などについて検討が進められていくことが期待されます。
|
 |
災害が突然起こったとき、自分自身や家族の生命・財産を守り、被害を最小限に抑えるためには、一人ひとりの普段の備え「自助」と、地域の人々による助け合い「共助」がとても重要です。
災害時に、自分や家族を守るため、日頃から食糧・飲料水の備蓄や防災訓練への参加などに努めましょう。 |
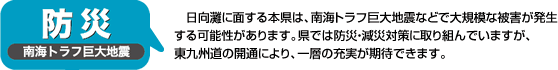
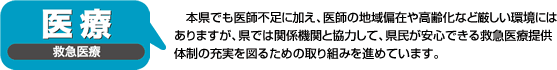
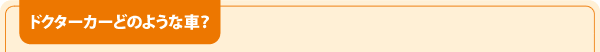
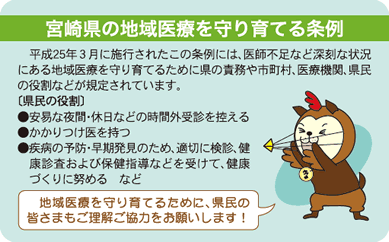
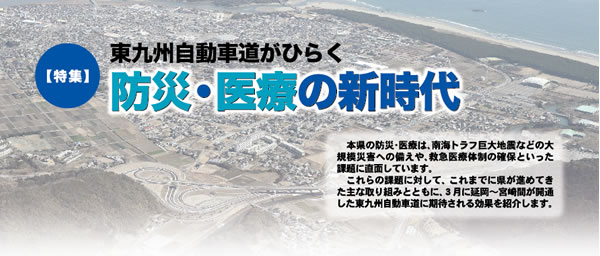
 (1)命の道としての高速道路
(1)命の道としての高速道路 (2)実践的な総合防災訓練の実施
(2)実践的な総合防災訓練の実施 (3)避難所としての高速道路
(3)避難所としての高速道路 (5)広域連携体制の強化
(5)広域連携体制の強化 ドクターヘリを活用した迅速な救急医療提供体制の強化
ドクターヘリを活用した迅速な救急医療提供体制の強化 【宮崎大学医学部附属病院と県立宮崎病院のドクターカーの役割】
【宮崎大学医学部附属病院と県立宮崎病院のドクターカーの役割】 【宮崎の救急医療に加わる若い力】
【宮崎の救急医療に加わる若い力】