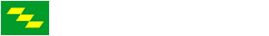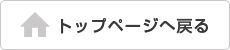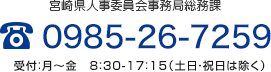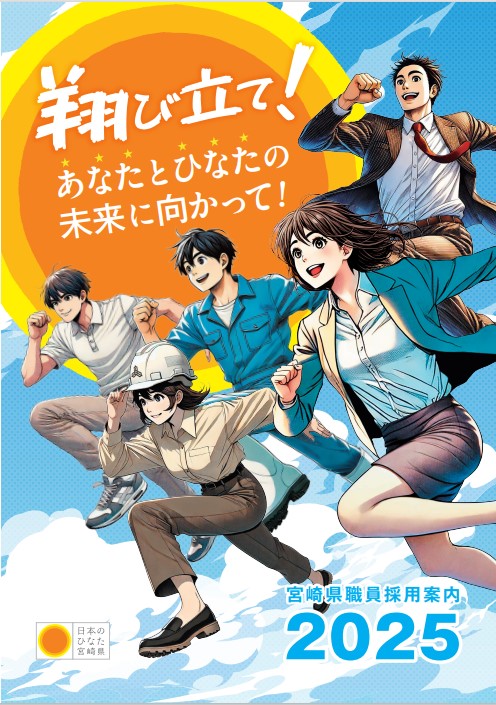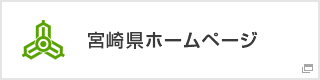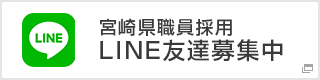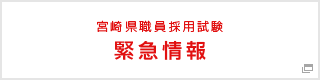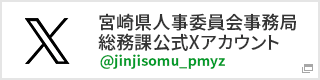出産・育児のための休業・休暇制度
県では、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備しています。
子どもが産まれる時
出産休暇
- 産前(出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合14週間))
- 産後(出産日後8週間)
配偶者出産休暇(男性職員のみ)
配偶者の出産による入退院の付添いや出産時の立会い時等に3日以内で取得可能
育児参加休暇(男性職員のみ)
配偶者の出産前後や、その出産の子又は小学校就学前の子どもを養育する場合→養育のため5日以内で休暇を取得可能
子どもが産まれてから
育児休業
子どもが3歳に達する日まで休業できる制度。男性職員も取得可。
休業期間中、給与は支給されない。(ただし、育児休業に係る子どもが1歳に達する日まで、共済組合から育児休業手当金として給与の約60%分が支払われる)
育児短時間勤務
小学校就学前の子どもの養育のため、通常(週5日・38時間45分)より短い時間で勤務できる制度。男性職員も取得可
勤務パターン
- 1日当たり3時間55分×週5日(週19時間35分)
- 1日当たり4時間55分×週5日(週24時間35分)
- 1日当たり7時間45分×週3日(週23時間15分)
- 1日当たり7時間45分×週2日、1日当たり3時間55分×週1日(週19時間25分)
- 1週間当たり19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分(交替制勤務の職員のみ)
給与
勤務した時間の割合に応じて支給される。
その他にも取得可能な休暇
1.育児時間休暇
生後満1年に達しない子を養育する場合→1日1時間以内で休暇を取得可能。男性職員も取得可
2.子の看護等休暇
中学校就学前の子どもが病気にかかった時の看護や学級閉鎖、子の行事参加(入園・入学式等)の場合→看護のため年5日(子どもが複数の場合は10日)まで休暇を取得可能。男性職員も取得可
3.妊娠中又は出産後の保健指導等休暇
母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合→必要な時間取得可能
4.妊娠中の通勤緩和休暇
交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合→1日1時間以内で休暇を取得可能
5.つわり等の妊娠障害のための休暇
妊娠に起因する障害のため勤務することが困難な場合→7日以内で休暇を取得可能
6.出生サポート休暇
不妊治療のために通院する場合など→年5日(体外受精や顕微授精を受ける場合は10日)
先輩職員からのメッセージ
第一線で活躍されてる方、子育てと両立しながら仕事をされている方、そんな先輩方からお話しを伺いました。